- 99ブロ TOP
- 洗車
- 足回り(タイヤ・ホイール)
- 冬に向かっての準備 その2 ~下回りのサビ対策~
2009年11月17日
冬に向かっての準備 その2 ~下回りのサビ対策~
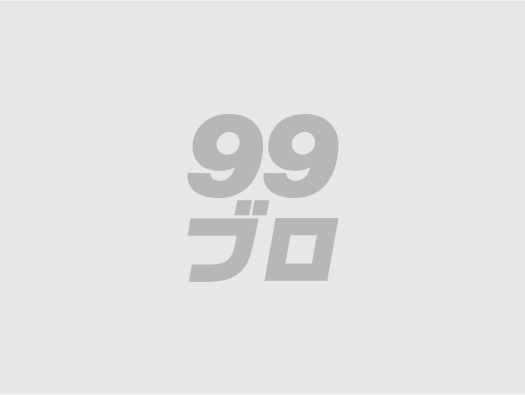
こんにちは。
ソフト99のミヤカワです。
寒いです。
我が家の昨夜の外気温は7度。
朝はきっと3度くらいだったんじゃないかと思います。
そして今日は大阪は雨です。
もう少し上空の気温が下がれば、雪も見られるんじゃないでしょうか。
雪が降ると出勤不可能になる可能性がある山奥なので、少し期待をしているのも事実です(笑)
さて、前回は同タイトルにて「朝の焦り軽減策」として、朝の凍ったウインドウ対策で解氷剤をご紹介させていただきました。
さて今回はクルマの下回り編。
みんカラユーザーの皆様は、下回りというと何を想像されますでしょうか。
いわゆるボディの底部や、タイヤハウスなどなどを想像していただければ、今回のテーマと合致してくると思います。
普段はあまり気にもしないし目にもしない部分ですが、冬になると、この部分が大変厳しい環境下に置かれるのです。
その原因が、この画像の中に潜んでいます。
さて、なんだか想像がつきますでしょうか。
答えは路面に撒かれた「凍結防止剤」。
この凍結防止剤、その正体は主に塩化カルシウムという物質が有名です。
塩化カルシウムは、水に添加すると凝固点(氷になる温度)を低くすることができるという特性を持ちます。
これによって0度以下になっても凍らず、水の状態のままなので路面の凍結を防止できるという仕組みなんですね。
しかし、いいことばかりではありません。
これがいわゆる「塩害」と呼ばれるものを引き起こしてしまうからです。
「塩害」とはよく海に近い土地で聞く言葉で、農作物などにも使われる言葉ですが、クルマに関わる害で言うと、例えば鉄の物体が普通より早くサビてしまうなんていう症状があります。
それと同じことが、凍結防止剤に含まれる成分によって起こってしまうということなんです。
凍結を防止することによって道路を安全に保ち、クルマを走らすことができる、というのは最も大事にすべきこと。
でも、クルマ(というより鉄)に対して過酷な環境の道を走らせるなら、クルマに耐性を持たせておくことが必要です。
そこで出てくるのが「塗装」。
塗装が「クルマの保護」と「美観維持」という2つの役割を果たしているのはご存知のとおりです。
もちろん、それは普段あまり目に付かないし気にしない部位であっても同じ。
塗装を施すことで、物理的に害のあるものとクルマを構成する鉄との接触を断ち、守ることができるからです。
下回りにはその環境に合った塗装が施されています。
重視されるのは、耐久性、防錆性、耐衝撃性。
たとえば、ホイールハウスからでも覗くことができる、フェンダーの内側の塗装は、巻き上げる砂や小石に耐えるために、膜も厚くクッション性の高い弾力のある塗装が用いられています。主にタイヤの影響範囲にある部分に施されています。
それが「アンダーコート」
また、車体の底部など、外装色の塗装が施されていない部分には、ブラックのサビを防ぐ塗装が施されています。
それが「シャーシーブラック」
もちろん新車の時点で、サビを防ぐための塗装はすでに施されています。
しかし、走らせていれば、小石の跳ねで剥がれてきたりする箇所があります。
そこからサビが発生すると…後々取り返しがつかない事態に。
昔は車検を受けるときに、防錆塗料の再塗装は必須でした。
今は鋼板がよくなったために、そのような規定はなくなったようですが、今も昔もサビがクルマの大敵であることにはかわりありません。
冬を迎えるまえに、まずは一度下回りをチェック!
長く愛車と付き合うためにはサビは大敵。
気になる部分はしっかり再塗装してサビ対策を施しておきましょう。
そして月に1度は、下回りの水洗いをオススメします。
※下回りをチェック、塗装する場合はジャッキアップ等の作業が必要になります。
危険が伴う作業となりますのでジャッキスタンドなど安全作業のための道具のご用意をお忘れなく。
自信のない方はディーラーや自動車整備工場へ相談することをおすすめします。
最新記事
-
月別アーカイブ











