2009年11月9日
「洗車研シャンプーS21体験記」その5 S21を実際に使ってみる!
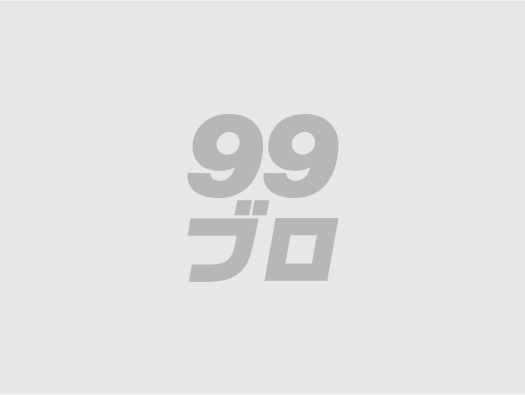
こんばんは。
ソフト99広報室のミヤカワです。
洗車にはいい季節から、若干寒い季節に移り変わりつつあります。
洗車にこだわる方々にむけてポツリポツリと進んでいる、この「洗車研シャンプーS21体験記」ですが、今回いよいよ(ようやく)最終回。
前回は、油汚れを取り去り、理想の下地を作り出すことをS21がいかにして達成しているかというメカニズムについて、お話させていただきました。
今回は実際にS21を使用しながら、その特長を洗いだしていくことにします。
まずセット内容。
・シャンプー
・スポンジ
シャンプーの液剤については、前回までで取り上げてきましたが、組み合わせるスポンジもなんでもいいというものではありません。
ボディに優しく洗うために「傷つきを抑える」「泡立ちを助ける」というテーマのもと、液剤との相性まで考慮に入れてスポンジを選定しました。
写真ではわかりにくいですが、スポンジのセル(網目状になっている部分)が非常に細かくできています。
ここを細かくすることによって、スポンジ内により多くの水分を保持することができ、かつシャンプーの泡立て時の発泡を助け、きめ細かい泡立ちを実現することができます。
液剤とスポンジの相乗効果で発生する泡は、ボディを優しく洗うために欠かせない重要な鍵を握っています。
それは
・洗浄成分を汚れに浸透させる効果
・汚れを物理的に包み込む効果
・汚れをボディに再付着させず、流し去る効果
の三つです。
一方で、流すときには泡切れが良ければ良いほど、シャンプーとしての使い勝手はよくなります。
この相反する条件を満たすためには、スポンジとの相乗効果までを考慮に入れた液剤設計が重要となるのです。
また、S21は原液を直接スポンジにとって使用するタイプ。
この方式には賛否両論ありますが、これにも理由があるんです。
その理由はカンタン。
「成分が薄まってしまうから」
成分が薄まるということは、化学的なアプローチによって油分を除去するというS21にとっては性能を十分に出せないということになってしまいます。
「使い勝手」と「性能」をはかりにかけた結果、S21では性能に重きを置き、原液を直に使用する方式を採用しています。
さて、洗うときはクルマの上部(ルーフ、ボンネット、サイド…)から順番に洗っていきます。
S21の場合は成分が強いので、シミになってしまったりするトラブルを避けるためにパーツごとの洗いとすすぎを推奨しています。
そしてS21使用時に限らない、シャンプー洗車の鉄則ですが、上から順番に洗うことで汚れた泡が洗った部位に触れることを避け、汚れの再付着を防ぐことができます。
さて、S21シャンプー後のクルマの表面は…
このように油分による水ハジキはなくなり、ベタッとしたものになりました。
S21による洗車後は、このように表面が脱脂された「スッピン」状態。
ワックスやコーティング剤が塗装面に密着しやすい施工環境を作り出しています。
しかし一方で、この状態のまま放置することは非常に危険。
必ず、ワックスやコーティング剤でのアフターケアをしてあげてください。
アフターケアには「洗車研コーティング剤B01」を是非!
うまくまとまったところで、長らくお付き合いいただきました「S21体験記」もこれにて終了です。
ココから先は是非一度お使いになっていただき、その性能をご自身の目で体感いただければと思います。
————————————————
今回、実際に一緒に使用した研究者が、一通り使用後にぼそっとつぶやきました。
「ボディの表面の油分はこれで除去できてます。理想的な施工環境は出来てるんですが、実はもうひとつ、除去したいものがありまして…」
…ここまできてそういうこと言いますか。
このシャンプーではまだ不足なんですか?
「いや、そんなことはないんですよ。S21はS21で所期の目的を達成しています。しかし、他にもいろいろと…」
どうやらまだまだ、研究の余地があるようです。
「ま、ちょっといろいろ調べてから、またお話させてもらいます」
思わせぶりな言葉を残して去っていく研究者。
一体彼らの頭の中には、どんな次の構想が練られているのでしょうか。
詳細が明らかになり次第、またこのブログでお伝えしていきたいと思います。
「洗車研」次のニューアイテムをお楽しみに!
最新記事
-
月別アーカイブ











