2009年7月13日
「洗車研コーティング剤B01」体験記5~「こんなところもこだわってます!」~
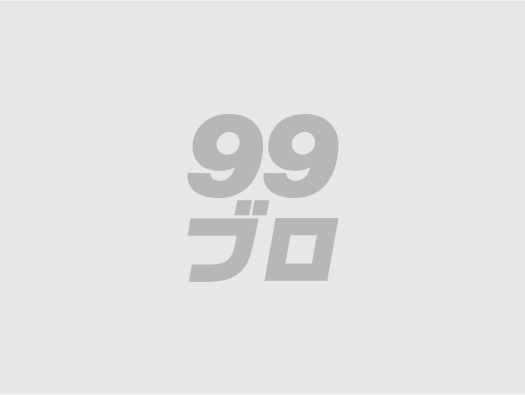

こんばんは。
ソフト99広報室のミヤカワです。
「洗車研(センシャラボ)」のカテゴリで、「洗車研コーティングB01体験記」と称して、製品そのものの詳細なレポートを試みておりますこのコーナーもいよいよ(一旦)最終回!
今回は「そんなところまでこだわってるんですか!」と思わず私が思ってしまったB01のポイントについてお話ししようと思います。
その1:吹きつけのスプレー部分「トリガー」
トリガーといいますと、この部分
いわゆる吹き付けの役割を果たす部分のことです。
一見、どこにでもありそうなこの部分ですが、この部分にもこだわりがあります。
それは、「液剤の性能をより引き出しやすくする」トリガーであるために、1回の噴射量、噴射の細かさ、噴射の範囲が重要になります。
このタイプのコーティング剤の基本構造として、分散した有効成分(樹脂など)の表面に、水の膜がはりついているものの集合体が液剤としてボトルに入っています。
液剤を、細かい霧状でボディに吹き付けてやることにより、液剤自体の表面積が増え、水の膜が蒸発しやすくなります。
この水の膜が蒸発すると、中から有効成分が出てきてボディにコーティングが定着していく、という仕組みなんです。
今回、この「B01」で使われているトリガーですが、選考にあたっての要件は
「ひと吹きで、できるだけ細かく霧状となって、かつたくさん出る」
というポイントでした。
このさじ加減が、施工のしやすさ(作業性)やムラの出来不出来(仕上りのよさ)に関わってきます。
その2:拭き取りのクロス
トリガーだけでそれができるわけではなく、塗り込みに使うクロスとの相乗効果が重要です。
それが
コレ。
マイクロファイバークロスです。
クロスの役割は、「液剤の余剰成分を拭き取り、ムラなく仕上げる」こと。
「B01」の場合は、洗車後の水と一緒に成分を拭き取る仕組みなので、余剰成分だけでなく、水も一緒に吸い込むことができることが重要です。
この辺は、クロスの繊維構成によって、より水を吸水しやすいものと、液剤成分を吸いやすいものと、いろいろな性格のものがあるので、チョイスによってはまったく思ったような仕上がりにならない場合があったりします。
また、マイクロファイバークロスの一般的な特徴として「かきとり性が高い」という性格があります。
今回「B01」に関しては、汚れ落としは済んでいるもの、との仮定の上で、付属の専用クロスはボディへの攻撃性は極力弱く、かつ水とコーティング余剰成分の拭き・吸い取りのバランスの良いモノを採用しています。
「このへんはしっかり選択しないと、性能が出る出ない以前の問題なのよ」
とは研究開発者の弁。
実際、クロスやトリガーに関してはかなり研究しているようで、先日テスト場にお邪魔したときも複数のトリガーを試験しておりました(冒頭の写真がそうです)。
そんなこんなで、これは「B01」には限りませんが、性能を最大限に発揮させるためには施工方法や道具に関しても妥協することなく、日夜研究が重ねられています。
さて、長らくお付き合いいただいた「B01体験記」もこれで一旦最終回!
少しは「B01」について、ご理解いただけたでしょうか?
次回からは、「洗車研」もうひとつのアイテム、「洗車研シャンプーS21」についてレポートしていきたいと思います!
最新記事
-
月別アーカイブ











